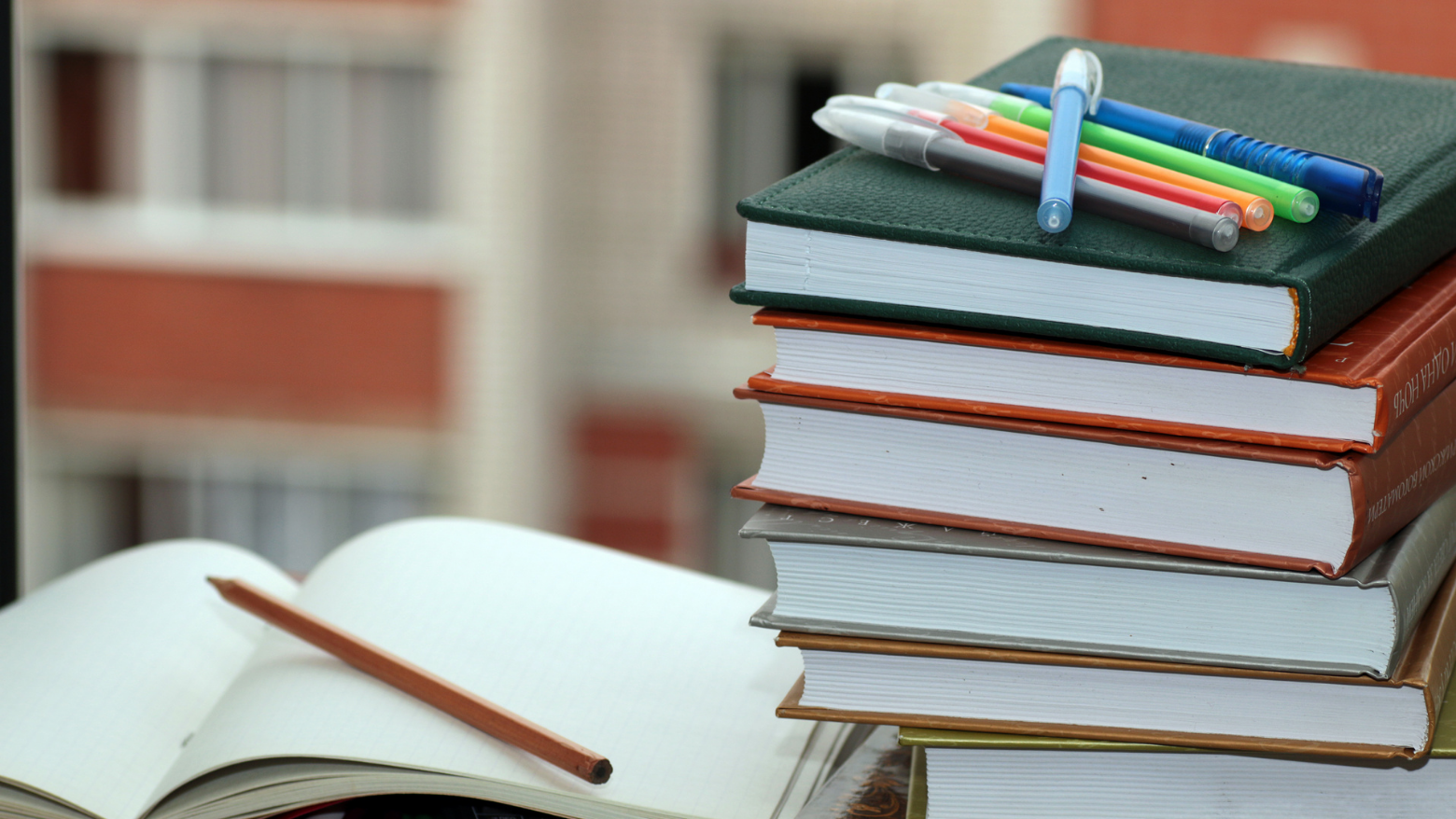Child Poverty
子どもの貧困
What is Child Poverty?
子どもの貧困とは?
貧困の問題は「お金」だけではありません。国連開発計画(UNDP)では、貧困(ひんこん)を「教育、食料、保健医療、飲料水、仕事、住居、エネルギーなど、最も基本的な物・サービスを手に入れられない状態のこと」と説明しています。こうした困難な状況では、自分の人生に希望をみいだしたり、自信を持ったりすることも難しくなってしまいます。
子どもの貧困は、世界中で教育・食料・医療といった基本的な権利を奪い、「貧困の連鎖」を生んでいます。一方、日本でも相対的に貧しい家庭に育つ子どもが多く、学習機会や心の健やかさに影響が出ています。フリー・ザ・チルドレン・ジャパンでは、こうした貧困の実態を世界と日本の両面から伝えることに重点的に取り組み、子どもたちが安心して成長できる社会をめざして活動を進めています。
引用:国連開発計画HP
世界と日本の子どもの貧困
世界では教育や食料、医療が不足し、命と未来が脅かされている子どもが数億人います。日本でも、社会の中で相対的に不利な状況に置かれた子どもが、学習や生活に制限を受けています。これらは「貧困の連鎖」を生み、次世代にも深刻な影響を与えます。
国連開発計画(UNDP)では、教育・住まい・食料・医療など人間らしい生活に必要な条件が欠けている状態を「貧困」と定義しています。特に子どもは成長段階にあり、食料不足は発育不良や病気のリスクを高め、教育の欠如は将来の就労機会を奪います。国際的には、学校に通えない、働かざるを得ない、十分な医療を受けられない子どもたちが多数存在します。
一方、日本における「子どもの貧困」は主に相対的貧困を指し、世帯の所得が中央値の半分未満である家庭の子どもをいいます。進学や部活動への参加を諦めざるを得ない、十分な食事を取れない、家で安心できる居場所がないなど、日常生活に深刻な影響が出ています。表面化しにくい問題であるため、周囲から理解されず孤立する子どもも少なくありません。
「貧困」の種類・考え方について
貧困は単なる数字では測れません。さまざまな原因が複雑に絡み合い、人々の生活に深く影響しています。そのため、世界では複数の指標や視点が用いられています。ここでは代表的な分類を紹介します。
慢性的貧困と一時的貧困
・慢性的貧困:貧困状態が何年、さらには何世代にもわたって続く状態。教育や雇用の機会不足など、構造的な要因が背景にあります。
・一時的貧困:災害、感染症の拡大、戦争、景気変動など、外的要因によって一時的に貧困に陥る状態。コロナ禍で生活が急変した家庭もこれに含まれます。
(参考)多次元貧困指数(Multidimensional Poverty Index:MPI)
考え方や計算方法が非常に複雑ですが、教育を受けていない・上下水道や電気が通っていない・テレビや冷蔵庫、電話、車などを保有していないなど、お金以外の貧困状況を数値化して調査・比較する「多次元貧困指数」という指標も、政府・国際機関などで用いられています。
(参考サイト)
・内閣府HP「子供の貧困に関する新たな指標の開発に向けた調査研究 報告書 第2章 諸外国における子供の貧困に関する指標の状況(2.2.2)」(2017年3月)
・世界銀行「貧困と繁栄の共有2020:運命の逆転」(英語) 全文pdf(29ページ・pdfデータ上では51ページ)
貧困がもたらす深刻な影響
貧困状態になると、人が生きていくために欠かせない食料や水、衣類、住居などが十分に手に入らず、また医療や教育といった社会サービスも受けられなくなります。特に子どもは栄養失調や不十分な食事により、心身の正常な発育・発達が妨げられ、病気にかかりやすくなるため、子どもの貧困は非常に深刻です。
さらに、病気になっても医療費や交通費が払えず適切な治療を受けられないケースや、そもそも医療施設や医療従事者が不足している地域もあります。こうしたインフラや資源の不足は、貧困の原因にもなっているのです。
教育の面でも、多くの子どもが学費や教材費を払えず学校に通えなかったり、空腹や栄養不良で授業に集中できずに中退してしまったりする現状があります。教育を受けられないことは、将来の安定した職に就く可能性を減らし、貧困の世代間連鎖につながります。また、近年のオンライン教育の普及に伴い、スマートフォンやパソコン、インターネット環境を持たない子どもたちの教育格差も広がっています。
こうした状況は、児童労働や人身売買、児童婚などの人権侵害につながることもあり、子どもたちの未来を奪う重大な問題です。心の面でも、貧困は自己肯定感の低下やメンタルヘルスの悪化を招き、社会参加や将来の生活にも悪影響を及ぼします。
貧困の背景にあるさまざまな原因
貧困は単一の問題ではなく、多くの社会課題や環境問題と密接に関連しています。病気やケガ、感染症の拡大は収入減少の原因となり、インフラの未整備や医療・教育資源の不足は貧困を悪化させます。さらに、適切な技術や知識の不足が生産性を下げ、貧困からの脱却を困難にしています。
差別や格差、社会的排除も貧困の要因であり、特にジェンダーや人種、障害などに基づく不平等は、生活の質や機会に大きな影響を与えています。また、自然災害や気候変動による資源の枯渇、環境破壊も貧困を生み出す要因です。例えば、漁業や農業が生業の地域での資源減少は収入減に直結します。
紛争や戦争も多くの人を貧困に追い込み、基本的な社会サービスの停止や難民化を引き起こしています。こうした状況は経済の混乱を招き、世界中の貧困問題を一層深刻にしています。
Background
活動の背景
貧困は子どもたちの「学ぶ権利」「育つ権利」「生きる権利」「参加する権利」を根本から奪います。世界と日本の両方で、将来への可能性を閉ざされる子どもたちの現状を変えるために、私たちは行動を起こしています。
国際社会が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)では、すべての子どもが貧困や飢餓から解放されることが重要課題とされています。しかし現実には、開発途上国では教育・医療・水へのアクセスが限られ、子どもたちは生き延びるために働き続けています。これが世代を超えた「貧困の連鎖」を生みます。
日本でも、経済的な困難が子どもたちの学習や体験の機会を減らし、自己肯定感や将来への希望を失わせています。親が低収入や失業に苦しむことで、家庭内のストレスや虐待リスクも高まります。私たちは、こうした貧困の影響が子どもたちの一生に及ぶことを深く憂慮し、国内外での活動を展開しています。
Our activity
私たちの活動
フリー・ザ・チルドレン・ジャパンは、海外と日本の双方で子どもの貧困の解消をめざし、教育・健康・生活環境の改善や自立支援を行っています。子どもたちが自らの未来を切り拓けるよう、知識・スキル・機会を提供しています。
海外では、教育を受けられない子どもたちのために学校を建設し、教員研修や教材支援を行っています。安全な水の確保や保健医療サービスの提供、家計を支える収入向上プログラムも実施し、地域全体で貧困から抜け出す力を養います。
日本では、経済的に困難な家庭の子どもに学習支援や食事支援を行う団体と連携し、教育の継続と心のケアを支えています。また、子ども自身が社会課題について学び、意見を発信できる機会を提供し、「助けられる存在」から「変化を起こす担い手」へと成長できるよう後押ししています。

海外自立支援事業
フィリピンやインドなどの開発途上国で教育・医療・水・収入向上を柱に地域の自立を支援。学校建設や職業訓練、衛生改善を通じ、子どもと家族が貧困から抜け出し、持続可能な暮らしを築く力を育んでいます。

国内自立支援事業
日本の子どもたちが経済的困難に負けず、自ら未来を切り拓けるよう学習支援や食事支援、社会課題を学ぶ機会を提供。地域や学校と連携し、子どもが「変化の担い手」として成長できる環境づくりを進めています。

講演・出前授業・ワークショップ
小学校、中学校、高校やその他教育機関や青少年団体にて、児童や生徒や学生が、世界と日本の貧困について学び考えることができる教材を開発し、講演やワークショップをしています。

外部団体との連携
子どもの貧困を解決するためのネットワークを広げて、活動しています。
Solution
解決に向けて
国連が掲げる持続可能な開発目標(SDGs)では、最初の目標として「貧困をなくそう(NO POVERTY)」が掲げられています。これは、貧困に苦しむ人々が必要な医療や教育、仕事の機会を得られるよう支援することを意味しています。