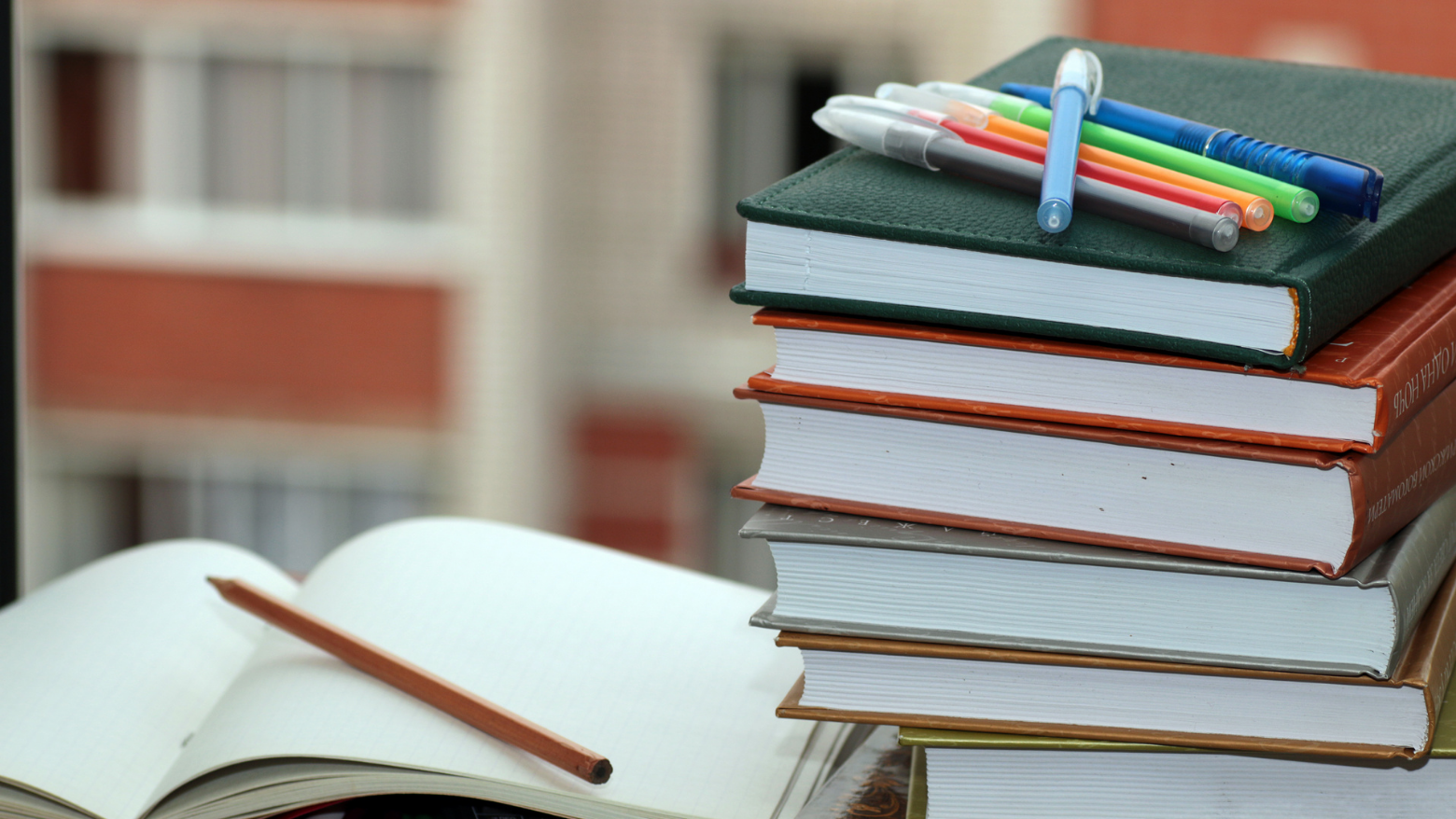Child Labour
児童労働
What is Child Labour?
児童労働とは?
働くことで心や体が傷ついてしまうような、子どもにとって害のある仕事のことをいいます。例えば、学校に通うことができずに働かされたり、法律で禁止されている危険な仕事に子どもが関わっていたら、それは児童労働です。つまり、児童労働は、子どもの権利をうばう、子どもに有害な労働のことです。
2025年6月11日に発表されたILO(国際労働機関)とユニセフ(国連児童基金)の報告書「CHILD LABOUR GLOBAL ESTIMATES 2024, TRENDS AND THE ROAD FORWARD」によると、世界には約1億3,760万人(うち約57%・7,800 万人が男子、約43%・5,900 万人が女子)の子どもが児童労働に従事しています。そのうち5,400万人が、子どもたちの健康や安全、発達を脅かす可能性のある「危険有害労働」にたずさわっています。
2020年の世界の児童労働者数は、新型コロナウイルスの影響により、残念ながら20年ぶりに減少傾向から増加に転じてしまいましたが、2024年の推計で減少傾向へ戻りました。しかし、世界各地で相次ぐ戦争、気候変動による災害の増加、経済不安など、児童労働者数が増えかねない要因が未だ数多く残っています。
日本でも、児童労働は労働基準法で禁止されていますが、近年SNSで子どもが騙されて詐欺や強盗などの犯罪に加担させられる「闇バイト」が大きな問題になっており、日本政府が対策を強化しています。
多くの子どもが農業分野で働いています。農業は子どもにとって非常に重労働で危険な仕事です。炎天下のなか体に害のある農薬や肥料を使ったり、鋭い刃物で収穫作業をしたり、重たい収穫物を運んだりしなければいけません。
日本は約60%の食糧を海外からの輸入に頼っています。私たちは児童労働で生産された食べ物を知らないうちに食べているかもしれません。
日本で想像する労働条件と違って、児童労働に従事する子どもたちは、8 時間以上働いても1 日1米ドル(約140円)も手に入らない場合が多くあります。子どもが長時間働いても収入が低いのは、年齢が低く、大人に都合のよいように利用されてしまうからです。
収入の例
- フィリピンのごみ山でゴミ拾い:運が良ければ100 円以上
- インドの靴工場で働く:1日8時間労働で約80 円
- 鉱山で金を採掘する:300 円もらえることもあれば、全く稼げないときもある
“最悪の形態の児童労働”とは?
最も過酷で危険な労働とされているものです。
- 人身売買(お金で子どもを売買すること)
- 性産業での労働(ポルノ、買春)
- 麻薬の製造・密売などの不法行為
- 子ども兵士
- 強制・債務労働(借金を返すために、奴隷のように働かされること)
児童労働はあるの?
一番の原因は貧困ですが、それだけではありません。
- 伝統や慣習
- 社会や雇い主の「子どもは働いて家族を支えるべき」という考え方
- おとな(親)の認識がたりないこと
- 法律の不十分な施行(しこう/せこう)
- 法律があっても十分に取り締まりや監視が行われていない
- 安い労働力への需要
- 教育の機会、設備の不足
- 国の政情が不安定
- 紛争、災害
- 親が病気やけがなどで働けない
- その他
- 国の政策が不十分で、子どもの権利や心身の健康・安全を最優先に考えていない
- 第一次産業(農業・林業・漁業)依存型の経済
- 都市に情報や経済が集中する格差社会 など
そして、児童労働が貧困を生んでいるのです
Background
活動の背景
フリー・ザ・チルドレンは、12歳のカナダの少年クレイグ・キールバーガーが、奴隷のように働かされる子どもたちの現実に衝撃を受け、「子どもとして何かしたい」と行動を起こしたことから始まりました。現在、フリー・ザ・チルドレン・ジャパンはその志を受け継ぎ、教育支援、生計向上、啓発活動を通じて児童労働の撤廃を目指しています。
児童労働に立ち向かうきっかけ
フリー・ザ・チルドレンの活動は、1995年、カナダに住む12歳の少年クレイグ・キールバーガーが一つの新聞記事に出会ったことから始まりました。それは、パキスタンで児童労働の実態を告発した末に命を奪われた、同い年の12歳の少年の話でした。 衝撃を受けたクレイグは現地を訪れ、学校に通えず、危険で過酷な労働に従事する子どもたちの姿を目の当たりにします。学びや遊ぶ時間を奪われ、貧困から抜け出す機会すらない現実に、「子どもにも世界を変える力がある」と信じて、仲間とともに行動を広げていきました。 この想いが、フリー・ザ・チルドレンの原点です。
児童労働の現状と私たちの役割
国際労働機関(ILO)の報告によると、現在も世界には約1億3,800万人、つまり13人にひとりの子どもが児童労働に従事しています。1995年当時は、6人にひとりにあたる約2億4,600万人もの児童労働者がいました。多くの人々や団体の取り組みによって、数は減少しましたが、児童労働は今もなお深刻な課題です。 この現実を見過ごすことはできません。 児童労働の問題を知ることは、まずその背景を理解し、私たちの暮らしとのつながりに気づくことから始まります。そして、子どもたちが安心して学び、遊び、未来を描ける社会をつくるために、私たちにできることを考え、行動していくことが求められています。 フリー・ザ・チルドレン・ジャパンでは、こうした思いのもと、児童労働のない世界を目指して様々な取り組みを行っています。
Our activity
私たちの活動
児童労働は、極度の貧困、教育機会の欠如、政治的意思の不足、不平等な社会構造など、さまざまな要因が複雑に絡み合って生じています。フリー・ザ・チルドレン・ジャパンは、この問題の根本的な解決を目指し、海外では教育支援や地域全体の生計向上を軸とした国際協力事業を展開し、国内では啓発活動や世論喚起を通じて政策提言を行うなど、両面から取り組んでいます。
たとえば、親が安定した収入を得られるよう、農業技術の向上や小規模ビジネスの支援を行い、子どもが働かざるを得ない状況を根本から変える支援を行っています。また、日本国内では、児童労働が遠い国の話ではなく、私たちの暮らしともつながっていることを伝える啓発活動を展開。学校やイベントでの講演、ワークショップ、教材提供などを通じて、消費行動と児童労働の関係を学び、持続可能な選択を広げる機会をつくっています。

講演・出前授業・ワークショップ
小学校、中学校、高校やその他教育機関や青少年団体にて、児童や生徒や学生が、児童労働について学び考えることができる教材を開発し、講演やワークショップをしています。


Towards Realization
解決に向けて
児童労働は、貧困や教育の欠如だけでなく、社会のしくみや私たちの消費行動によっても生まれています。でも、変える力は、私たち一人ひとりにあります。 小さな気づきが、大きな変化につながります。知ること、伝えること、選ぶこと——そのひとつひとつが、子どもたちの未来を守る一歩になります。ここでは、解決への第一歩「現状について知ること」について紹介します。