ウェルビーイング


ウェルビーイングってなに?
みなさんは、ウェルビーイングという言葉を聞いたことがありますか? ウェルビーイングは英語でWell-beingと書きます。「幸福であること」と訳されることが多い言葉ですが、直訳すると「well」は良い、「being」はその状態がつづくこと、つまり、「良い状態であること」という意味です。では、「良い状態」とはどういうことなのでしょうか?
私たちフリー・ザ・チルドレン・ジャパン(FTCJ)では、ウェルビーイングを:
「一人ひとりが人権を大切にされ、こころやからだや、周りとの関係や、社会の中での自分の存在が、自分にとってちょうど心地よい状態、または、そこに向かう過程のこと」と定義しています。

生きていると、良いことばかりではありません。むしろ、つらいこと、悲しいこと、ムカムカすること、イヤなことがたくさんあります。だから、私たちFTCJでは、「良い状態がずっとつづくこと」をめざすのではなく、イヤなことや悲しいことが起きたときに、どうやってその気持ちに向きあったらよいのかや、自分にとって心地よい状態が何かを考えることが、大切だと考えています。そして、それこそが、ウェルビーイングなのです。
私たちがなぜ、「ウェルビーイング」の活動にとりくむのか
気分が落ち込んで、やる気がおきない…
自分に自信がないし、将来は不安ばかり…
目標や理想を実現しようとがんばっているけれど、うまくいったりいかなかったり…
そんな声を、子どもや若者のみなさんから聞くことがあります。そして、最近、そういった声が増えてきたように感じています。
実際に、日本の警察から、2022年や2023年に自殺した10代は、今までの統計の中で一番多かったと発表されました。悩みがあるけれど、だれにも相談できず、一人で抱えてつらい想いをしている子どもや若者のみなさんが多くいることに対して、何とかしなければいけないと、思ったからです。
なぜなら、人はだれしも、「幸せになる権利」があるからです。子どもでも若者でも、だれでも大切な社会の一員です。だから、私たちFTCJは、子どもや若者が、自分にとってのウェルビーイングを見つけられるよう、サポートをする取り組みをすることにしました。
子どもや若者のみなさん、ぜひ私たちと一緒に、ウェルビーイングについて考えていきましょう。
なぜ、人は悩み、落ち込むのか。
色々なことに悩みながら日々モヤモヤを抱えて過ごしていませんか?でも、そんな気持ちを抱えているのは、決して、あなた一人ではありません。
10代は、こういったモヤモヤを抱えることは自然なことで、このモヤモヤには理由があります。有名なアメリカの心理学者エリクソンによると、人は、生まれてから年老いるまでの発達段階ごとに、向き合い、乗り越えなければならない課題があると言われています。これを「心理社会的発達段階理論」といいます。
悩んで、迷って、モヤモヤした先に、「これが自分!」が見つかったら青年期を卒業して、次の段階「成人期」に進みます。
みんな何かに悩んでる。
気分が落ち込んで、やる気がおきない…
自分に自信がないし、将来は不安ばかり…
目標や理想を実現しようとがんばっているけれど、うまくいったりいかなかったり…
10代の悩みやモヤモヤについて様々な調査報告があります。みんなの心のなかをちょっと覗いてみよう。
ウェルビーイングには脳のしくみを知ることが大切。
「脳のはたらき」とウェルビーイングのつながり
人間がこの地球にあらわれたのは、なんと600万年前だといわれています。とても長い時間ですね。でも、今のように電気があって、車やスマホがある便利な生活が始まったのは、ほんの最近のことなんです。
たとえば、600万年の人間の歴史を「1年のカレンダー」にたとえると、工場や電車ができた「産業革命」から今の社会までの時間は、12月31日の午後4時すぎくらい。つまり、私たちが知っているような暮らしは、歴史の中ではほんの“さいごの数時間”にすぎないんです。
だから、私たちの体や脳は、まだまだ「自然の中で生きのびるためのしくみ」をたくさん持っています。これを知ることは、「ウェルビーイング」を考えるうえでとても大切です。
マンモスに出会ったらどうする?〜脳のサバイバルモード〜
昔の人たちは、森の中でマンモスやライオンのような大きな動物に出会うことがありました。そんなとき、すぐに「にげなきゃ!」と体が反応できるように、脳は“びっくりスイッチ”を入れて、体を戦うか逃げるかのモードに切りかえてくれます。
このしくみを「闘争・逃走反応(とうそう・とうそうはんのう)/Fight or Flight Reaction」といいます。今の私たちはマンモスに出会うことはありませんが、テストや人間関係などでストレスを感じたとき、脳は同じように「体と心を守るモード」に切りかえてくれます。心臓がドキドキしたり、汗をかいたりするのはそのためです。


扁桃体は、小さな問題にも大きな問題にも同じように作動します。何かを恐れていることを考えるだけで、「戦うか・逃げるか」の反応を起こさせます。

複雑な思考をつかさどり、計画を立てたり、組織化をしたりします。

新しい学習や記憶をつかさどります。
だからこそ、自分の脳と仲よくなろう
脳は、私たちを守るためにがんばってくれています。でも、いつもびっくりスイッチが入りっぱなしだと、心も体もつかれてしまいます。だからこそ、自分の脳のしくみを知って、「今、どんなモードかな?」と気づくことが、ウェルビーイングにつながるんです。
ドキドキ、あせあせ…それって「ふつう」のことなんだよ
たとえば、テストの前や人前で話すときに、心臓がドキドキしたり、手に汗をかいたり、呼吸がはやくなったりしたことはありませんか?
それは、あなたの脳が「この場面はちょっとたいへんかも!」と感じて、体を“がんばるモード”に切りかえてくれているからなんです。これは「ストレス反応」といって、誰にでも起こるごく自然なこと。あなたが特別に弱いとか、変だというわけではまったくありません。
「自分を知ること」が、心と体をととのえるカ
だから、ストレスを感じたときに「なんでこんなふうになっちゃうんだろう…」と落ちこむ必要はありません。むしろ、「あ、今わたしの脳ががんばってるんだな」と気づけることが、とても大切なんです。
自分の脳や体のしくみを知って、「今、どんな反応が起きてるのかな?」とやさしく見つめること。それが、ウェルビーイング――心と体が「自分にとってちょうど心地よい状態」になるためへの第一歩です。
ウェルビーイングな暮らしをおくるために
ウェルビーイングな暮らしをおくるためのヒント集
このヒント集では、悲しみや怒りなどを感じたり、気持ちが大きく揺れ動いたときに、うまくその感情とつきあっていくコツや、毎日の生活をウェルビーイングに近づけるためのアイデアと簡単なワークを紹介しています。
このヒント集で紹介しているコツやワークを、日常にとりいれられそうなところから、やってみてください。
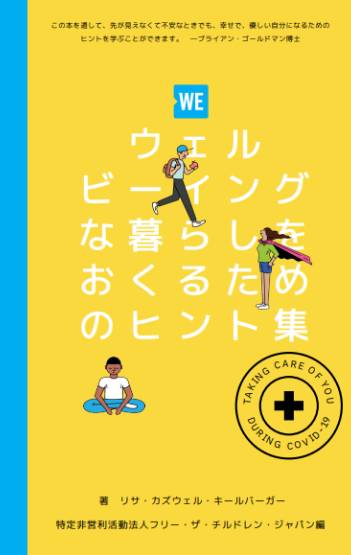
翻訳・編集・発行者:認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン
対象:中学生以上
ページ数:216ページ
判型:B5変型(176 × 250 mm)
形態:電子書籍(pdf形式)
ファイルサイズ:14.7MB
ウェルビーイングな暮らしをおくるための各種窓口
あなたはここで紹介する情報・団体・人などにつながることができますが、つながるのをやめることもできます。他の選択肢を探すことや選ぶことも自由です。もしもそのような自由が許されないようなことを言われたり制約を受けたりするようなことがあったら、それはあなたの人権が守られていないことを意味しています。あなたが安心して話せたり、相談したりできる場所が見つかったら、自分のペースでつながってみてください。
チャイルドライン
(無料 12/29〜1/3を除く毎日16:00~21:00)
かかえてる思いを誰かに話すことで、少しでも楽になるよう、気持ちを受け止めます。あなたの思いを大切にしながら、どうしたらいいかを一緒に考えていきます。お説教や命令、意見の押し付けはしません。
24時間子供SOSダイヤル(文部科学省)
(無料 12/29〜1/3を除く毎日16:00~21:00)
いじめや不登校で悩んでいたり、自分や友人の安全に不安があったりしたら、いつでもすぐ電話で無料相談ができます。専用電話番号にかけると各地教育委員会の相談機関が、24時間体制であなたの相談に応じます。こどもと保護者が利用できます。
こどもの人権110番(法務省)
(無料 12/29〜1/3を除く毎日16:00~21:00)
友達から「いじめ」にあって学校に行きたくない、家の人にいやなことをされる、部活動で暴言・暴力を受けているなど、先生や親には話しにくいときや、「まわりでこんなことで困っている人がいる」という相談もOK。無料で電話相談できます。
子どもの人権に関する相談窓口一覧(日本弁護士連合会)
お父さんやお母さんにたたかれる、友達に無視される、つらい思いや苦しい思い、あなたが悩んでいることについて、弁護士が相談にのります。相談は無料です。名前は言わなくても大丈夫です。秘密は守ります。あなたが住んでる場所を選んでください。(住んでいる場所ではないところでも相談もできます。)詳しくはWEBサイトに地域別の連絡窓口があるのでアクセスしてみてください。


